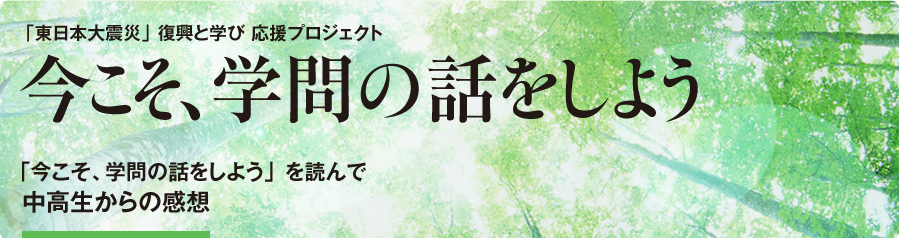【 2.社会の基盤を支える 】
【 2.社会の基盤を支える 】本当の学びは、未知の解を見つけるために「問い」続けること
鈴木 直義 (静岡県立大学/情報教育)
-----------------------------------------
■震災直後、あらゆる報道で「未曾有の大震災」「想定外だった」などというフレーズを耳にした。私はその言葉を何の抵抗もなく受け止めていたが、今回鈴木先生のお話を読み、自分が間違っていたことに気づかされました。この大震災によって起きた事柄を「想定外」などという言葉で片付けてはいけないのです。震災から6カ月経つ今でも、様々な理由で苦しんでいる人がいます。事実から目をそむけず、これから先このようなあるいはこれ以上の災害にも瞬時に対応し、被害者を出さない社会にするべきだと思います。(中3・女子・R.W)
------------------------------------------
■鈴木先生の考えに同感した。解のある問題に取り組み、その解を導くことも大切だと思う。しかし先の見えないこれからの未来を歩む時、つまり解のない問いにぶつかる時、これまでの能力とはまた違う能力が必要になる。私は大学とは自分の専攻を深める場であると考えてきたがそれだけではないことがわかった。大学とは、自分のまたは社会の課題に向き合い「未知の解」を探るために自身の内面を見つめ問い続ける苦しさを味わい、困難なことに耐え抜く能力を鍛える場だった。(高2・N.E)
------------------------------------------
■本当の勉強というのは、何度も問い続けることだということに気づかされた。そしてそれを続けることの苦しさを耐え抜く力をつけるところが大学だと言うこと。高校では解が決まっていてそれを「まねと記憶」によって問題を解いていくけれど、現実社会問題はそうではないということを知った。大学であらゆる事に対処できる力をつけて社会貢献したい。(高2・女子・M .I)
------------------------------------------
■人の話を鵜呑みにして、考えない人間にはなりたくないと思いました。実際生きて行く上で不測の事態なんていくらでも起こりうるし、それに対応していかなければいけません。答えが用意されていないのは当たり前だから、ワンパターンに物事を考えてはいけないと改めて認識できました。(高2・男子・sphere.K)
------------------------------------------
■「問い」続けることの大切さを知りました。テストのため、誰かのために学ぶのではなく、自分のために学ぶことが大切だと思いました。今までやってこなかった、という言い訳はしたくないので精一杯がんばりたいです。(高2・女子・Y.A)
------------------------------------------
■「想定外」「前代未聞」「未曾有」といった現実味のないことが起こったとき、自分が臨機応変にその場で最善を尽くすことができるのか考えさせられた。「勉強なんて、はっきり言って高校までで十分ではないのか」と思うことがある私に大学に向かう良い刺激となった。机に向かうだけの勉強ではなく、環境に適応した「学び」をしていきたいと思った。(高1・女子・N.M)
------------------------------------------
■私は学びというと高校で習った正解が確定した問題だけだと思っていましたが、このメッセージを読んでそうではないとわかりました。実際私は今回の震災が「想定外」で何も行動することができませんでした。だから私は新たな経験に挑み続け高校での学びをクリアして、大学で本当の「学び」と受けたいと思います。(高1・男子・T.K)
------------------------------------------
■今回のこの災害が高校生活の応用版だと考えていることにとても関心をおぼえました。先生が言っている通り、高校生活にはない、100点満点の解などどこにない問題が今回の災害対策だと思いました。だからただ点数にとらわれているだけで高校生活をとどまっているのではダメだと思いました。(高1・男子・H.Y)
------------------------------------------
■僕が震災後思うことは、自分なりにこの出来事について多くの人に知ってもらおうと行動しなければならないということです。このような大震災がよく起こるものではなく、体験者がいなくなってしまった後起きることが多いことが、被害を拡大させていると思います。今はまだ多くの人が警戒していると思います。周りにその恐ろしさを伝えてくれる人がたくさんいるからです。これから100年後同じことが起こったら、今のままでは今回の震災の二の舞になってしまうと思います。だから自分たちの子ども、孫の世代にも震災経験者として伝えていけるようにします。それが義務だと考えています。1000年後これ以上の震災が起こっても「想定内」だといえるような国をつくっていかなければならないと思いました。同じことは戦争についても言えることだと思います。(高2・男子・聞見百倍)
------------------------------------------
■大学へ行く意味はいろいろありますが、メッセージを読んでさらに増えました。私は未知の解を見つけることから逃げ出しがちになりますが、大学では未知の解を見つけるために「問い」続ける苦しさに耐え抜く能力を育てたいです。そして新たな経験に積極的に挑みたいです。(高2・女子・Y.K)
------------------------------------------
■「これからは確定した答えを見つけ出すだけではなく、未知の解を見つけるために問い続ける」というのを読んで、それは難しそうだと思うと同時に面白そうだなと思った。大学は大変そうだけど早く行きたいと思った。(高2・男子・M)
------------------------------------------
■「解があるかどうかさえ定かでなく、100点満点の解など望むべくもない課題にとりくむことが現実社会では求められているのです」。自分の中にはこの一文がとても印象に残っています。今の社会には未知の解を見つけるために「問い」続ける苦しみに耐える能力が著しく低いと思います。(高2・男子・K.R)
------------------------------------------
■鈴木先生がおっしゃっている通り、今回の東日本大震災は誰も予想していなかった本当に想定外の出来事でした。私たちの日常では想定外の出来事はほとんどありません。今回のように想定外の出来事が起こったとき、人々は皆気が動転して、普通の考えもできなくなります。想定外のことが起こっても大丈夫なようにいろいろな対処法を考えておく必要があると思いました。(高2・女子・えんどー)
------------------------------------------
■「現実の課題に立ち向かい、未知の解を見つけるために『問い』続ける苦しさに耐え抜く能力を育てる場が大学」ということが印象に残り、色々な新たな経験に挑んでいこうと思った。(高2・女子・N.A)
------------------------------------------
■高校でやることは無駄ではないが、それは全て真似と同じであるということに私も共感した。新しいものを得るためには自分の経験とそれを得るための努力が必要だと思った。大学は新しいものを生み出すところなのかもしれない。(高2・男子・K.T)
------------------------------------------
■素直に学校で教わっていることを反復させるだけなのをやめない限り、自身の可能性はその範囲内で、その範囲外のことに対応できなくなってしまうことに気づくことができました。(高2・男子・F.)